
会社と社員の理想的な関係 ~落語「百年目」から考える
今回は、古典落語「百年目」から、会社と従業員の理想的な関係について考えます。落語の話ですが、この文章にオチはありませんのであしからず。
こんにちは、社長の藤田です。
私の数少ない趣味の一つに、古典落語を聴くことがあります。趣味と言っても、車の中で落語のCDを聴き、テレビ番組「笑点」を見て、年1回行けたら寄席や落語会に行くという程度です。
百年目は、ある大きな商家で働く番頭が主人公で、奉公人である手代や丁稚、そして店の経営者である旦那らが登場する噺。番頭と奉公人との関係性、彼らの幸せを願う旦那の思いが描かれており、現代企業の人事マネジメントにも通じる内容です。
落語は同じ演目でも、演じ方、話の内容など、演者によってディテールに違いがありますが、今回は百年目を得意とした古今亭志ん朝さんについても触れたいと思います。
「百年目」のあらすじ
あらすじは次の通りです(オチについては今回のテーマと関係がないので割愛しています)。
長く勤めている番頭の次兵衛は、手代や丁稚ら奉公人に厳しく、すぐに叱り飛ばします。まあ、奉公人も、こよりを馬にして紙相撲で遊んだり、出すはずの手紙をそのままにしていたりと、叱られて仕方が無い要素はあるのですが…。
そんな堅物の番頭、店のみんなには隠していますが、実は相当の遊び人。ある春の日、太鼓持ちや芸者を引き連れて花見に出かけ、はた迷惑などんちゃん騒ぎを起こします。そこを偶然、友人と花見に訪れた旦那が通りがかり、番頭と鉢合わせ。慌てたのは番頭で、意味の分からないあいさつをしどろもどろに述べ、店へ帰って寝込んでしまします。
すっかり本性がばれてしまい、旦那の叱責を恐れ、いっそ店を辞めようかと一晩中思い悩む番頭。翌日、帳場に出ても仕事が手に付きません。そんな番頭を旦那が呼び立て、日ごろの働きぶりに感謝を述べた上で、次のような話を聞かせます。
天竺(今のインド)に、赤栴檀(しゃくせんだん)という立派な木が生えている。この木の下に、南縁草(なんえんそう)という草がはびこっている。南縁草は大変醜い草だが、刈ってしまうと立派な赤栴檀の木までもが枯れてしまう。
この赤栴檀は、南縁草を肥料にして枝を伸ばし続けている。そして赤栴檀が下ろす露は、南縁草にとってこの上ない栄養となる。
赤栴檀が番頭だとすると、奉公人は南縁草。うちの南縁草はちょっと元気がないようなので、もう少し露を下ろしてはどうかと、旦那は提案します。優しく諭された番頭はすっかり恐縮し、感動するのでした。
「立派な木」と「醜い草」のいい関係
あらすじを読み返して気付きましたが、噺を文字に起こしても、ちっとも面白さが伝わりませんね。ぜひ実際に鑑賞してみてください。
さて、ここから私の主観ですが、この赤栴檀と南縁草の関係こそ、会社と社員の理想的な姿だと思っていましたし、今でも思っています。
会社は社員の幸せを願い、利益や福利厚生を提供する。そして社員は会社に利益をもたらすため、ますます頑張って働く。
おそらくこの演目は、欧米で演じても共感を得ることはないでしょう。なぜなら、欧米は会社を渡り歩くのが当たり前だからです。終身雇用という固有の制度を採用している日本だからこそ、この噺が受け入れられるのだと思います。
「醜い草」にもなれず「根無し草」になった私
しかし、現実は落語のようにうまくいくとは限りません。
日本は世界との競争力を失ってしまい、先進諸国の中では特異とも言える賃金の上がらない国になってしまいました。赤栴檀はここ20年、南縁草に十分に露を下ろせていない状態です。それどころか、「リストラ」として役に立たない南縁草を駆除したり、「部署間異動」として生えすぎている南縁草を他の場所に移植したりしています。
前の職場で「前代未聞の異動」を経験した私は、さしずめ移植された南縁草でした。移植先でも赤栴檀に養分を上げようとしましたが、土や水が合わず、努力と能力も足りず、枯れる寸前にまでなってしまいました。植わっていた元の場所に戻してくれと赤栴檀に希望を出しましたがそれもかなわず、自らフリーランスという「根無し草」として生きていく道を選びました。
会社が頼れない時代になってしまい、南縁草のほうにも赤栴檀を盛り立てて行く気概はありません。期待に見合った働きをしない「働かないおじさん」と呼ばれる中高年社員が取り沙汰され、若手社員も会社への忠誠心を持たないのが当たり前となっています。
赤栴檀になれない会社、南縁草の役割を果たさない社員。お互いが「こんなはずではない」と思っているのではないでしょうか。
志ん朝の百年目ににじむ旦那の愛情
もう一度、話を落語に戻します。
この話は「大ネタ」と言われるほどの難しい話で、古来多くの名人上手たちが高座にかけてきました。
私自身も何人かの百年目を聴きましたが、一番好きなのが志ん朝さんです。あくまで個人の意見ですが、志ん朝さんの百年目には、旦那の奉公人に対する愛情がにじみ出ているのです。
奉公人は遊んだり、仕事を忘れたりと、決して優秀ではありません。番頭だけでなく、旦那自らも奉公人の言葉遣いに対し苦言を呈する場面もあります。しかし旦那は番頭に対し「奉公人に元気がないので、露を下ろしてやってくれ」「長い目でみてやってくれ」と、番頭のプライドを傷つけない範囲で説諭をするのです。
この旦那のように「長い目で見る」ということを、日本社会の赤栴檀も、そして南縁草も、いまいちど思い起こす必要があるのかもしれません。私自身も長い目で見ることを大切にし、「根無し草」から「栴檀の木」に成長していきたいと思います。
それにしても、志ん朝さんの百年目は何度聞いてもいい。絶品です。


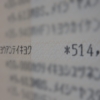

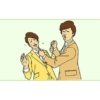



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません