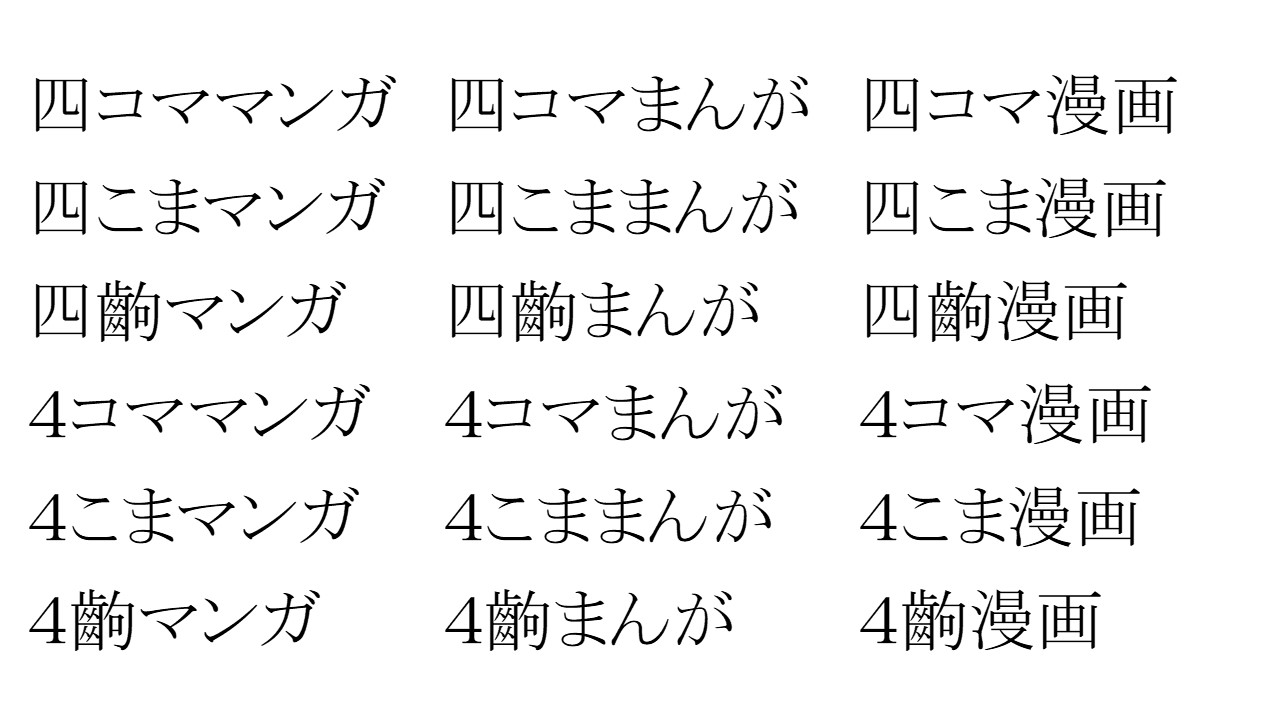
「4コマ漫画」か「4こま漫画」か ―文章を書く際のカタカナ表記の基準―
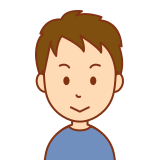
4こま漫画? 4コマ漫画では?
こんにちは、社長の藤田です。「学歴も会社も頼れない時代にどうやって生き延びるか」をテーマにしたブログを設け、仮面ライターさんと2人でフリーランスや転職、記者の仕事や文章の書き方について情報を発信しています。
ブログにアップする文章はそれぞれ見せ合ってチェックしています。私の文章を仮面ライターさんにチェックしてもらっていたとき、上のような指摘がありました。
「4こま漫画」と「4コマ漫画」。果たしてどちらの表記が正しいのでしょうか?
ライターの皆さんは記事を書いていて、ひらがなかカタカナかで悩んだことがあるでしょうか。理由もないけど、なんとなくカタカナにしているという方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、新聞記者とフリーライターで合わせて16年ほど書く仕事をしている私が、「記者ハンドブック」に書かれているカタカナ表記の五つの基準について紹介したいと思います。
ライティングの仕事において、言葉の表記についてはクライアントの意向や掲載メディアのルールに従うのが前提です。それでも、新聞記者が使っているルールを把握しておけば、ライティングで損になることはありません。
実際、記者ハンドブックを表記の基準に採用している雑誌やネットメディアも多くあります。この文章がライターの皆さんのお役に立つことができれば幸いです。
文章は 漢字・ひらがな交じりが原則
私は文章を書く際、表記のルールとして参考にしているのが「記者ハンドブック 新聞用字用語集」(共同通信社発行)です。新聞社にニュース記事を配信する共同通信社をはじめ、全国の地方新聞社で記事を書く際のルールとして採用しています。
この中では「新聞記事の大原則」として、次のように定めてあります。
文章は(中略)現代仮名遣いによる漢字・平仮名交じり文を主体にし、必要に応じて片仮名、ローマ字を使う。
共同通信社発行「記者ハンドブック 新聞用字用語集」第13版 7ページ
つまり文章を書くときは漢字とひらがなを原則とし、カタカナとローマ字はあくまで補助的な使用にとどめるとしています。
確かに、「文章ハ(中略)現代仮名遣イニヨル漢字・平仮名交ジリ文ヲ主体ニシ、必要ニ応ジテ片仮名、ローマ字ヲ使ウ」とカタカナ主体の文章は読みづらいですよね。
カタカナ表記を採用する5パターン
それでは、カタカナはどのような場合に使うのでしょうか。記者ハンドブックでは、カタカナ表記を採用するパターンがあちこちに書かれていますが、それらをまとめると次の5パターンに整理することができます。
①外来語
海外由来の言葉です。記者ハンドブックでは以下のように定められています。
<引用>外来語は片仮名で書き、原音に近く、同時に日本語に読みやすい表記を用いる。ただし慣用の固定しているものは、これに従う。
外来語が短縮されたもの(パソコン、インフレなど)や和製英語(ガソリンスタンド、カンニング、ニューハーフなど)も外来語に準じてカタカナで書きます。
②外国人名・地名(中国と朝鮮半島は除く)
「ジョン・バイデン」「デーブ・スペクター」「ニューヨーク」「ブエノスアイレス」など。
中国、韓国、北朝鮮関係の人名地名は除きますので、「習近平」「仁川」「平壌」と書き、「シュウキンペイ」「インチョン」「ピョンヤン」とは書きません。ただし「ソウル」「ハルビン」「マカオ」など、例外があります。
また、ホーチミンは「胡志明」と漢字で書けますが、中国と朝鮮半島から除外されますのでカタカナ表記です。
③オノマトペ
「オノマトペ」とは擬音語、擬声語、擬態語の意味。物の動きや人の感情、動物の鳴き声や物音などを表す言葉です。
このうち、擬音語・擬声語(ガーガー、キャンキャン)などは原則カタカナで、ひらがなでも可。擬態語(うっとり、ずきずき、にょろにょろ)は原則ひらがなで、カタカナでも許容されます。
④動植物名
動植物の名称は原則としてカタカナで書きます。
ただし、比喩的に使う場合や慣用句(雨後のたけのこ、つばめ返し、猫かわいがり、など)は漢字やひらがなです。
⑤その他
その他として、特別の意味やニュアンスを出す場合、読みにくさを避ける場合はカタカナを使ってもよい、とされています。
この文章では、「片仮名」をすべて「カタカナ」と記述しています。本来は漢字表記が本則ですが、カタカナが主役の記事なので、特に強調するためにカタカナ表記としました。
4こま漫画の「こま」は「齣」
それでは、冒頭に出した漫画は「4コマ」でしょうか、「4こま」でしょうか?
4こま漫画の「こま」とは「齣」という漢字が当てられます。「区切り」という意味を持つ、れっきとした日本語です。
このことから、上記①~④のカタカナ表記ルールには当てはまらず、⑤のように文脈上特別の意味を出す場合でもありません。さらに「齣」という漢字は難しいので、記者ハンドブック的にはひらがなで書くのが正解となります。
漫画も「マンガ」「まんが」と仮名書きされることが多いですが、これも日本語ですので、漢字で書くのが原則です。私も記者時代、原稿に「マンガ」と書いてしまい、注意を受けたことがあります。
余談ですが「4こま漫画」というルールに「4コマまんが」という表記が一番おもしろいような気がするのは私だけでしょうか。「4こまマンガ」だと何となく違和感がありますし、「四齣漫画」だともはや笑いのエッセンスが全くなさそうです。
他にもある ひらがな書きが「ルール上正しい」言葉
「4こま漫画」以外にも、カタカナ書きをよく見かけるものの、ルール上は一応ひらがな書きが正しい言葉は多くあります。つれづれなるままにいくつか例示します。
「ごみ」も「こんろ」もひらがな書き
例えば、捨てる「ごみ」や、台所にある「こんろ」など。一見外来語っぽいですが、それぞれ「塵」「焜炉」と漢字があり、れっきとした日本語です。ごみについてはカタカナ、ひらがなどちらでもよいという新聞社もあるようですが、日本由来の言葉なのでやっぱりひらがなで書くべきかと思います。
文章を書く「骨」
物事を行う際の勘所や要領のことを「コツ」と言いますが、これも日本語。「骨」という漢語が由来で、体の支える大切な役割というのが元の意味です。
鎌倉時代末期に吉田兼好によって書かれた『徒然草』にも出てくる、思った以上に古い歴史を持つ言葉です。
つれなく過ぎて嗜なむ人、天性、そ骨なけれども、
徒然草 第百五十段(能をつかんとする人)
「タバコ」か「たばこ」か「煙草」か
「タバコ」はスペイン語・ポルトガル語の「tabaco」から来ています。外来語なのでカタカナにしたいところですが、新聞表記では「たばこ」とひらがなになります。
理由については共同通信社に聞いてないので分からないですが、そもそもタバコが日本に伝来したのは戦国時代末期。江戸時代に徳川幕府が農民統制のために発した「慶安御触書(けいあんのおふれがき)」にも「たばこのみ申す間敷候」(たばこを吸ってはいけない)と表記があります。歴史が古い言葉ということで、ひらがな表記になっていると考えることができます。
ただし、植物としてタバコを表記(葉タバコ、タバコ畑など)するときは、ルール④によりカタカナ書きです。漢字の「煙草」は当て字なので、記者ハンドブックでは使用しないことになっています。
まとめ
今回は、共同通信社発行「記者ハンドブック 新聞用字用語集」より、ライティングでカタカナ表記を使う5つのパターンを紹介しました。
①外来語
②外国人名・地名(中国と朝鮮半島は除く)
③オノマトペ
④動植物名
⑤その他(特別の意味やニュアンスを出す場合、読みにくさを避ける場合)
「意味が通じればいい。表記なんてどちらでもいいじゃないか」と思った方もいらっしゃるかもしれません。しかし、言葉の使い方にこだわりを持つことで、洗練された文章が書けるようになるはずです。
表記の仕方について「これが正しい」という究極の正解はないと思います。しかし、言葉を操ってきた先人たちの英知が詰まった記者ハンドブックは、ライティングの際の心強い羅針盤になるのではないでしょうか。


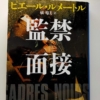





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません