
新聞記者はこうやって新聞を読む ー前編ー
新聞記者をリストラされ、小説とブログを書き続けている、「かく企画」社員の仮面ライターです。みなさんは新聞を読んでいますか?
私は50代が目前に迫っている世代です。大学生の頃、社会人が新聞を読むのは当たり前だと言われていました。今、通勤時間に新聞を広げている人を見るのは、北海道で沖縄ナンバーの車を目にするくらい珍しいのではないでしょうか。スマートフォンの普及や新聞社への信頼低下など、いろいろ原因があるのでしょう。
今回は「新聞を読んだほうが良いですよ」という話を書こうとしているわけではありません。
私はこの数年で新聞を読む時間が大幅に減りました。リストラによる心的な影響があり、あまり目にしたくないということもあります。でも、自分の生活にかかわる法律や制度の変更については、紙面を開いています。
若いビジネスパーソンで、新聞を活用している方は少ないのではないかと思います。新聞社の記者採用試験を受けに来た学生の中に、新聞を読んでいないという人が少なからずいる話をきいたことがあるくらいです。
それでも敢えて、新聞記者の新聞の読み方から、社会で生き残るヒントを得ていただければと考え、書くことにしました。「そんなことをやっているから新聞社はダメなんだ」と思う方がいれば、そこから教訓を汲み取っていただけたらと思います。
新人記者の方にも読んでいただけたらとてもうれしいです。
読み方は2種類 ―現場記者と整理記者―
この回で度々、「新聞を読む」という言葉が出てきます。新聞は、アプリや有料専用サイトで読むことが出来る「デジタル版」と、昔ながらの紙があります。この回のブログで「新聞」といった場合は、基本的に紙の新聞を指します。
新聞社には、大まかに2種類の記者がいます。取材現場で仕事をしている「現場記者」。現場には行かず人が書いた記事の価値判断をして、紙面の掲載場所を考え、見出しやレイアウトを決める「整理記者」がいます。
後者は新聞社によって呼び方は違うようですが、「整理部」という部門が昔は一般的だったので、「整理記者」といえば、「ああ、内勤の人だな」と新聞社の人はわかるはずです。
上記の2種類以外にも、「校閲記者」もいます。現場記者が書いた原稿(※新聞社では、新聞に載る前のものを原稿と呼びます)を監修するデスクもいます。
現場記者の読み方 ―ビジネスパーソン向け(初級編)―
現場記者も細かく見ると、多様な担当があります。政治部や経済部などに所属して、専門分野について大都市中心に取材する人たち。各都道府県の取材拠点で、事件・事故、市町村の地域政治・経済、街の出来事などを取材する人たち。スポーツ部に所属して、プロスポーツを取材する人たち。
色々な職種があるのですが、これら現場記者が新聞を読む目的の一つが、「抜かれチェック」です。
「抜かれ」というのは、自分の担当分野で、他の報道機関に先んじて書かれたり、放送されたりすることを言います。現場記者は、抜かれていることがわかると、その時点から取材(※他社の記事を跡追いするので、「追っかけ」とも言います)を始めなければならないのが基本です。
新聞社の速報性について、ネット時代にどれだけ重要なのかは甚だ疑問です。ただ、いち早く報じようとする姿勢は、ほぼ変化していません。また、他の報道機関が書いたものを今後の参考にするため、速報の観点以外でも「抜かれチェック」をしています。
「抜かれチェック」を目的にした読み方は、担当分野の記事が掲載されているページを読むことです。例えば、私が宮城県の担当をしています。全国紙であれば、県のニュースを扱うページが1、2ページ分あります。
朝起きてなるべく早く、自分が勤めている新聞社以外のニュースを確認します。もちろん、宿直勤務をしている記者が知らせてくれることになっているのが通例ですが、忘れられたり、抜かれと気づかず連絡が来なかったりということもあります。そのために、読む必要があるのです。
基本的に、誰かが自分のことを守ってくれるなんてことは想定しない方が良いのかもしれません。
自分のエリア外のページを読む意味
紹介したように、現場記者は、自分の担当分野について、よその新聞社の記事を読みます。読むというよりは、自分が知らないことを書いていないかを探します。前の日に一緒に取材をしても、知らない要素が書かれている時があります。
時に痛い失敗があります。上記の例のように、地域ニュースのページだけチェックをしていたら、ほかのページ(例えば、政治のページ)に、自分の担当している話が書かれていた、なんてことがあります。
地域の政治も、重要度が高まったり、時の政権にからむ要素があったりすると、政治のページに掲載されることがあるのです。ですから、担当ページだけ確認していると、「抜かれチェック忘れ」という、痛い思いをすることになります。
まとめ ービジネスパーソン向け読み方ー
ビジネスパーソンで、短時間で情報収集をしたい方には、現場記者の読み方がおすすめです。
自分が「記者」になった気持ちで、他社(他者)が先んじて商品を開発したり、ビジネスを前進させたりしている事例がないかをチェックします。
日本経済新聞の場合、ビジネスに関するニュースを一般紙より、さらに細分化してカテゴライズしています。デジタル版は検索ができます。紙の場合は一覧性があるので、「抜かれチェック」のついでに、仕事のヒントになる記事を目にするチャンスがあるのが長所です。
「上をいく記者」はちょっと違う読み方をしていた
上記で紹介したように、現場記者の新聞を読む目的の第一は、抜かれチェックです。私は、かなりずぼらでしたので、抜かれているかどうかだけ見て、終わりというのがほとんどでした。
ところが、ちょっと上をいくレベルの記者たちは違いました。
新聞は最初のページを「1面」と言います。次のページは「2面」です。日本経済新聞のような専門紙ではない、多くの新聞の場合、1~4面くらいは、「総合面」などと呼びます。
特ダネを見つけるのは、「夜討ち朝駆け」と言われる、朝一に取材対象に人の家に行ったり、夜に帰りを待ち伏せて話を聞き出したりすることだけが、方法ではありません。
「総合面」を読んでいると、これから先、どんな話が重要になってくるかがわかります。
都道府県の取材網を担当している人で、特に行政取材の担当者ならば、これらのページを読んでおくと、感度が高まります。例えば、あなたが愛知県の記者で、新型コロナウイルスの感染拡大防止について取材しているとします。防止策の緩和について、「自民党内の専門部会で話し合いが始まった」という話だと、「4面」に小さく乗ります。次に、「自民党が公明党から了承を得られた」となると、もう少し扱いが良くなります。
自民党内でまずは話し合い、与党内で地固めをする、というように、政策の実現性が高まるほどに、ニュースの扱いは大きくなります。法案を国会に提出という段階になると、社会面に、防止策緩和に反対する医師や市民の話が掲載されるようになります。
「3面」「4面」に小さく書かれている記事。それが、あなたの担当分野で特ダネになる可能性があるのです。愛知県担当の記者であれば、県庁の担当部局がどのような対応をするかを取材すれば、特ダネになる可能性が出てきます。
アドバンスドレベルの読み方はカスタマイズ
記者ではない方の場合、アドバンスドレベルの読み方は自分の生活やその日の忙しさに合わせるほうが長続きします。
忙しくて、どうしても新聞を読む時間がないということはあります。その時は、必要なページを切って保存しておき、休みの日に読むに読むのはどうでしょう。ただ、「抜かれチェック」的な記事は、その日のうちに目を通してしまうことをおすすめします。短時間で出来ることですが、1週間分ためると、面倒になってしまいます。
他の新聞社の記者で、中身の濃い記事を書いたり、特ダネをよく書いたりする記者にどんなことをしているのか聞いたことがあります。
毎日、自社の新聞は全ページ呼んでいる
その人が言っているとおりに私は出来ませんでした。もし、すべてのページを読むならば、3、4時間はかかると思います。取材の合間に読んでいたのだと思います。根気が必要です。
ネットニュースの効果的な活用法
もう一つ、参考になる情報収集の仕方をしていた官僚のお話を紹介します。この方は、ネットニュースの重要性を認識し、どうやって情報収集するかについて教えてくれました。
「Yahoo」のトップページに出ている記事を定時にチェックする
という方法でした。Yahooのトップニュースは8つあり、バランスが取れているそうです。
ネットニュースは、次々と関連記事が出てくるので、確認していると終りがありません。そこで、Yahooのトップニュース8つを中心に時間を決めて読んでいるとのことでした。
次回は、「整理記者」の読み方について書きたいと思います。



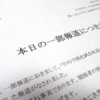


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません