
新聞記者はこうやって新聞を読む ー後編ー
今回は、新聞記者の新聞の読み方を紹介する後編です。
前回は、新聞記者には、「現場記者」と「整理記者」がいるという説明をして、「現場記者」の読み方について書きました。ちなみに、私は、「現場記者」と「整理記者」のどちらも経験しています。最後は、「現場記者」をしていましたが、戦力外通告を受け、第二の人生を歩み始めています。
「学歴も会社も頼れない時代にどうやって生き延びるか」というテーマのこのブログ。フリーランスで独立することや副業収入を目指す方に役立つスキルなどを紹介しています。今回は新聞の読み方について考えたいと思います。
「新聞を読みましょう」という結論ありきで書いているわけではありません。もし、このブログの内容に違和感がある方は、どこがダメなのかを考えていただければ、反面教師になると思います。担当は、「かく企画」社員の仮面ライターです。
現場に行かない整理記者の読み方
前回は、現場で取材をする記者の新聞の読み方を紹介しました。今回は、整理記者の読み方です。
整理記者の新聞の読み方は、まるまる読みです。1ページから最後のページまですべて読みます。そう聞くと、大変だと思う方がいると思います。実際に大変です。とても時間がかかりますし、休みの日も読まなければなりません。
最近は「働き方改革」の影響もあり、新聞社の整理記者の働き方が、かなり違ってきていると聞いています。私が紹介する読み方は、少なくとも10年くらい前までの話になります。
不人気部署だった整理部 今は人気部署?
そもそもですが、私が整理記者の頃、整理部は不人気部署でした。多くの人は、現場記者でいたいと思い、人事異動が出るとがっかりしたという人が大半でした。中には、退職してしまう人もいました。
アラフィフ世代の私ですが、20、30代の頃の新聞記者は、大都市以外の2か所で計4年くらい働いた後に、大都市に行きました。その時に、政治部、経済部、社会部、スポーツ部、学芸部など、呼び方は新聞社によってそれぞれですが、それまでの評価などに基づいて振り分けられました。
人気があったのは、政治部や外報部。外報部は、いきなり入れる例は少なく、政治、経済、社会のそれぞれの部で経験を積んでからという感じでした。
何れにせよ人気がなかった整理部。最近は、そうでもないと聞いています。休みがシフト制なので、現場記者よりまともな生活が送れること。また、大都市を中心に異動するので、引っ越し回数が限られるなど、生活を考えての選択です。
全ページ読破 睡眠時間が4時間に
私の場合、整理部の中でも格下扱いの地域ページ担当でした。今、その部署は、人員削減と経費削減のために子会社化されてしまいました。
整理部に異動と聞いてがっくりし、さらに来てみると、格下部署だと知り、当時の私は荒れました。 「整理部本流」に異動になったのは、それから数年後でした。
「整理部本流」で働くようになって言われたことがあります。
新聞を毎日すべて読め
整理部に休みはない
「新聞を毎日すべて読め」について話をします。どうして、修行僧のようなことをしなければいけないのか?すべてのページを読むと、最初は5時間くらいかかりました。夕刊もあります。たまに読むなら悪くもないのですが、毎日強制されると楽しくもありません。
出勤するために家を出るのが午後2時か3時。それまでに読み終えるためには、午前10時には読み始めないといけません。「なんだ。別にどうってことない」と思われるかもしれませんが、朝刊をつくる整理部の仕事が終わるのが午前2時すぎ。締め切り時間に追われて、頭をフル回転させた後は、すぐには寝付けません。午前5時に寝られたら良い方でした。ですから、10時に読み始めるためには、食事や家事の時間を考えると、4時間睡眠になってしまいます。
新聞社にはダースベーダーがいる
最初の1ヶ月は、まじめに4時間睡眠で必死に読みました。少しずつ速く読めるようにはなりましたが、それでも3時間半はかかりました。行きたくもなかった整理部。「整理部は楽だよ」と言われていましたが、ちっとも楽ではありません。
整理部本流には、映画「スター・ウォーズ」のダースベーダーみたいな恐怖感を与える上司がいました。仕事初めの時間帯に、新聞をちゃんと読んでいるかチェックしてきます。
「君、今日の第1国際面のカタ(※2番手の記事という意味)はなんだっけ?」
答えられないと、ジメジメといじめられます。
「ああ、そうなんだ。いいねぇ、新聞を読んでこないで出勤してくるなんて。なかなか楽しそうじゃない」
圧力をかけられ、自分の呼吸がダースベーダーのように、「コーホー、コーホー」と音を立てているように感じます。どんな必死に読んできても、そこまで覚えていないことがあります。でも問答無用です。
「まぁ、今日はゆっくりしていって下さい」。ライトセーバーでやられた心境でした。
スター・ウォーズの例えはさておき、どうしてすべてのページを読んでくることを課せられていたのか。表向きには、突発的な記事が飛び込んできた時に、とっさに価値判断が出来るようにするため、と言われていました。そうは言うものの、データベースがあります。その上、自分が価値判断をする以前に、デスク(※整理部にもデスクがいます)や、それよりも上位にいる筆頭デスクや、もっと上の当番編集長たちが、価値を決めてしまいます。
当時の私は、必死に読んでから出勤しようと努めました。でも、朝眠くて起きるのが遅くなって時間が足りなかったり、要領を覚えてスポーツ面は斜め読みしたりして、段々と手を抜くようになりました。手抜きをした理由の一つが、そこまでする意味を当時は、深く理解出来ていなかったからです。
人材育成
最終的な価値判断をするのは、その日の編集長やデスクたちです。しかし、そういう仕事がすぐにできるわけではありません。差配する仕事をするためには、トレーニングが必要です。
当番編集長をする人たちの出身は様々です。整理部出身だけではありません。社会部、経済部、政治部など、いろいろなバックグラウンドを持っています。私見ですが、社会部記者から社会部デスク、社会部長になったような、ガチガチの社会部畑の人は、編集会議であまり意見を言いません。社会部が取材することには詳しいのですが、それ以外はそうでもないからかもしれません。
一方、整理部出身の編集幹部は専門はありませんが、一般的になんでも知っているという感じで、どんな分野のニュースが飛び込んできても、判断軸がしっかりしていました。最終判断は幹部ですが、ヒラ整理記者も価値判断の意見を言うことがあります。それが聞いてもらえるかは別問題ですが。
自分で記事の価値判断をするという意識がないと、いつまでたっても判断力はつきません。そのためには、すべての分野についての情報をインプットする。つまり、読んでくるという作業が必要だという考え方です。
ニュースキャスター・久米宏さんと同じ仕事
私は、高校、大学生の時に、亡くなった筑紫哲也さんのニュース番組を見て、記者の仕事をしたいと思いました。筑紫さんは、政治の話だけではなく、文化にも詳しく、「なんでこの人はなんでも知っているのだろう」と思ったことを覚えています。
久米宏さんも夜の看板ニュース番組を担当していました。ご本人に聞いたわけではないので、そういう話が伝えられているという前提で、私が覚えている話を紹介します。
久米さんの番組が始まるのは、午後10時くらい。しかし、久米さんがテレビ局にやってくるのは、その12時間前だったというのです。番組本番まで何をしているのか?
新聞は全国紙だけでも数紙あります。農業新聞などの専門紙、スポーツ新聞、週刊誌を入れるともっとあります。久米さんは、新聞を丹念に読んで、今話題の小説などにも目を通す。時には、一度外に出て映画を見てくる。それだけの準備をしても、番組中に「これは」という一言が出てくる瞬間は、なかなかないということでした。
整理記者当時、新聞を読むのは嫌でした。でも、今思えば、あの久米さんや筑紫さんがしていることを、名もなき整理記者でしたが、やっていたのだと思います。
テレビ欄までも読んでくる
私は苦しんでいた全ページ読破ですが、同僚の中にはテレビ欄まで読んでくる人がいました。その人に新聞を読むコツを教えてもらいました。
一つは、紙面を作っている時に読んでしまうという方法です。整理記者は、掲載される前の段階の原稿から読むことが出来ました。原稿を真剣に読んでおけば、印刷された時にかなり時間を短縮できます。
もう一つは、帰宅前に配られる紙面で読んでしまうという方法です。締め切り時間後、輪転機が動き出してすぐに、点検用の紙面が整理記者には配られます。締め切り時間前後は、人はすごい集中力を発揮します。ですから、しばらくは記事を読むのが格段に速くなるのです。逆に、朝は頭が起動していないのでそうはいきません。
ですから、夜のうちにできる限り読み尽くしてしまえば、朝が楽になるのです。
「プチ宏」になっていた私
こうして、新聞をまじめに全ページ読むようになった数カ月後、卒業した大学の仲間と会う機会がありました。ゼミが一緒だった同窓生は、様々な組織で働いていました。旅行代理店、航空会社、市役所、商社、服飾業界。どの同級生の話もとてもおもしろくて質問が尽きません。すると、同級生の一人が私に聞きました。
「どうして、どの業界のことにも詳しいの?」
その頃は、まだ、まじめに新聞を端から端まで読んでいた頃です。自分では気がつかいないうちに、知識がつき、それぞれの業界の課題などについて興味を持つようになっていたのです。
大学生の頃、総合商社で働く2年目の人に話を聞かせて貰う機会がありました。その方は、「新聞は学生の時に読む習慣をつけるように」と、言っていました。確かに、整理記者以外にも幅広い知識や興味関心が必要な仕事はあります。学生の時くらい新聞を読んでみると、自分に変化があることを実感できると思います。
まとめ ー新聞を読む長所と短所ー
新聞は毎日、数十人の人が、山のようにあるニュースの中から、これは少なくとも報じなければいけないというものを選び、価値の順位付けを議論しています。
「新聞社になんか決められた価値なんて、まっぴらごめんだ」
そういう意見もあると思います。整理記者は、「普通」「一般的」という価値基準を持つことは簡単ではない、もしくは、そもそもそんなものはないことをわかっていると思います。(※私は少なくとも、「普通」「一般的」はないと思っていたので、整理記者の仕事はつらかったです)
それでも、生活をよくするために、整理記者は「これは知らなくてはいけない」というニュースを日々、迷いながら作っています。ベストなニュース媒体ではないかもしれないですが、ベターな情報の集合と言えるかもしれません。
そして、学校という教育機関を出た後、社会を知るための材料にはなります。結果として、物知りになります。それは、新しい分野の情報を仕入れなければいけないという時に役立ちます。多分野の知識があり、座標軸が定まっているので、新分野にも強くなれます。また、あなたが毎日、新聞を全ページ読もうとすれば、次第に活字を読むのが速くなります。
一方、短所です。新聞を読むのは時間がかかります。特に、すべてのページを読むならば、相当意識的に取り組まないと出来ません。もう一つは値段の高さです。月に4千円前後です。学生の人なら、スマートフォンや必要な有料アプリなどの代金を考えると、そんなお金は払えないと思うのではないでしょうか?
余談ですが、電子版は一部の社を除いて、比較的に安いです。ただ、「整理記者読み」をするのであれば、紙の方が良いです。電子版は、それこそ無限大にニュースがあると言ってよいほど、次から次へのニュースが出てきます。また、紙であれば、その日の朝刊を作るまでの時点でまとめられたニュースです。継続して読めば、取りこぼすニュースは原則的にありません。
長所と短所をまとめると以下のようになります。
長所
- 数十人が価値づけを毎日議論している
- 「普通」「一般的」と、迷いながら作られている。ベストではないがベターな情報
- 物知りになる
- 活字を読むのが早くなる
- 他の情報を仕入れる時に予備知識、座標があるので速くなる
短所
- 読むのに時間がかる
- 高い
なお、新聞さえ読めば良いとは私は思っていません。プラスアルファで、自分なりの情報を日々、仕入れていくことも大切です。一般知識と専門知識が備わって、良い仕事が出来るのだと思います。けっこう大変ですが……。



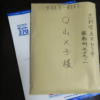

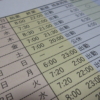


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません