
「焼肉」はなぜ新聞記事で「焼き肉」とおいしくなさそうに表記するのか
こんにちは、社長の藤田です。現在はフリーライターとしてさまざまな記事を書いていますが、かつては新聞記者として働いていました。
突然ですが、焼肉っておいしいですよね。
焼肉店の炭火七輪やロースターで焼くハラミやカルビはもちろん、食堂などの焼肉定食も美味。自宅でビール片手にホットプレートを囲み、エバラや日本食研の焼肉のたれに付けて食べるのもまた格別です。
焼肉店、焼肉定食、焼肉のたれ…。一般的には「焼肉」の表記が多いですが、新聞では「焼き肉」と書きます。個人的には「焼肉」のほうがおいしそうに見えますが、「焼き肉店」「焼き肉定食」「焼き肉のたれ」の表記です。
なぜわざわざ送り仮名を付けて、おいしくなさそうに表記するのでしょうか。理由を調べてみると、戦後日本を代表するある大物政治家の影が見え隠れしていました。
今回は、新聞表記と送り仮名について考察したいと思います。
食べ物などには「き」を送る、焼き物は送らない
地方紙などにおける新聞表記のルールを定めた「記者ハンドブック 第13版新聞用字用語集」(共同通信社)によると、食べ物など一般用語の場合は「焼き」と送り仮名を送ります。
小麦粉の生地にあんこを入れ、焼き型で焼いた「今川焼き」。地方によっては「大判焼き」などと言うことがありますが、これも「焼き」です。祭りなどの露天で売られる「カルメラ焼き」、朝ご飯のおかずの「目玉焼き」も送り仮名を付けます。
食中毒の記事で直された
かつて駆け出しの記者だったころ、焼き肉を「焼肉」と表記して、デスクから直されたことがあります。
「『焼き肉』よりも『焼肉』のほうがおいしそうなのにな…。あっ、でも食中毒の記事だから、おいしく書かないほうがよいか?」
そんなことを思いながら記者ハンドブックで確認したところ、確かに「焼き肉」と掲載されていました。
備前焼と素焼き
一方、地名などを冠した工芸品は、送り仮名を付けない「焼」。例えば、愛媛県の砥部焼、愛知県の常滑焼などは「焼」の表記です。
岡山県の特産品である備前焼は、釉薬を使わずに高温で焼くのが特徴で、素朴な風合いが人気です。こちらも「焼」の表記で「備前焼き」などとは書きません。
一方、同じく釉薬を使わない陶器である素焼きに関しては、地名を冠した工芸品ではないため「焼き」と送り仮名を付けます。
「焼き肉」の表記法を決めたのは田中角栄!?
食べ物と工芸品で、なぜこのような表記の違いが発生するのでしょうか。
送り仮名の付け方は、実は政府が決めています。1973年、当時の田中角栄内閣が国語表記の目安・よりどころとして内閣訓令第2号「送り仮名の付け方」というのを告示しています。
「焼肉」を「焼き肉」と表記するよう決めたのは、「今太閤」こと田中角栄氏であると言えなくもありません。
送り仮名の付け方の「本則」と「許容」
この「送り仮名の付け方」には、基本的なルールである「本則」と、例外を認める「許容」というのが定められています。
以下、詳しく見ていきます。
「本則」では、2語以上の言葉からできた複合語はそれぞれに送り仮名を付けることとなっています。焼き肉の場合、「焼く」+「肉」=「焼き肉」と送り仮名を付けます。
その他、いくつか例を挙げると…
入る+江=入り江
生きる+物=生き物
落ちる+葉=落ち葉
その上でこのルールには「許容」として、読み間違いの恐れがなければ送り仮名を省くことができるとしています。
この許容に沿うと、焼き肉、入り江は読み間違いの恐れがないので「焼肉」「入江」でもOK。首相を辞してなお「目白の闇将軍」と恐れられた田中氏ですが、焼き肉の表記に対しては意外と寛容だったようです。
一方で生き物や落ち葉は「せいぶつ」「らくよう」と誤読する恐れがあるので、必ず送り仮名を付けなければなりません。
「許容」を認めない原理主義者の新聞表記
ここで新聞表記に話を戻します。
記者ハンドブックによると、送り仮名の付け方は先に説明した内閣訓令第2号に基づいて、日本新聞協会の新聞用語懇談会が取り決めた方式を採用するとしています。
ところが同時に、内閣告示の「本則」に統一し、「許容」は採用しないとしています。つまり許容で使ってよいとされている「焼肉」の表記は認めないということです。大物政治家の田中角栄よりもルールにシビアな姿勢を取っています。
今川焼き、大判焼き、カルメラ焼き、目玉焼きについても同じです。
今太閤死してなお残る疑問
送り仮名の付け方のルールに田中角栄が関わっていた(厳密には文化庁の官僚か学者あたりが決めたのでしょうが…)のは新たな発見でした。さらに、「焼肉」の表記についても認めていた田中氏に対し、それを認めない新聞・マスコミの強硬な姿勢にも驚きです。
さて、本稿の前半で「地名などを関した工芸品は、送り仮名を付けない」と紹介しました。この理由を探ろうと内閣訓令第2号を読み返したのですが、「慣用に従って送り仮名を付けない」としか書かれていませんでした。
焼き物だけに限らず、輪島塗、友禅染、博多織などの伝統工芸品についても同じです。国はどのような基準をもって「慣用」といっているのでしょうか? そのあたりについては知ることができませんでした。
田中氏が亡くなってから丸30年。ロッキード事件の金の流れと同様に、日本語の送り仮名の表記についても、いまなお疑問は残っています。
まとめ
今回は、新聞表記と送り仮名についての話題でした。
おちゃらけながら説明してしまったため、分かりづらかったとおもいますので、最後に送り仮名の付け方の要点をまとめておきます。
①本則…2語以上の言葉からできた複合語はそれぞれに送り仮名を付ける
(例)焼き肉、入り江、生き物、落ち葉、今川焼き、カルメラ焼き
②許容…読み間違いの恐れがなければ送り仮名を省くことができる
(例)焼肉、入江
③③慣用に従い、地名などを関した工芸品は、送り仮名を付けない
(例)砥部焼、備前焼、輪島塗、博多織
新聞記事は①と③を採用し、②は採用しない。

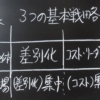



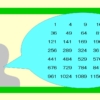

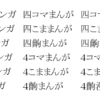
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません