
ホッチキスと日本の働き方
突然ですが、ホッチキスをどのようにとめるのが正しいと思いますか?
ホッチキスかホチキス、はたまたステープラーという名称がありますが、今回はその名称の正解は脇に置き、紙のとめ方についてです。
フリ―ランスや転職、副業に役立つスキルなどを考えるのが、このブログのテーマです。ホッチキスから今回は日本の働き方を考えたいと思います。
ホッチキスで怒鳴られた 社会人1年目
最初の問題ですが、答えは(※私が教えられた答え)は、「紙の左上のところに、針を斜めにしてとめる」です。
学校を出て最初に勤めた企業(※新聞社には転職で入社しました)では、お茶くみとコピー取りを若手の頃にしました。
お茶くみと言うと、織田裕二さんが主演をした「お金がない」という1990年代のテレビドラマを思い出します。
世界的な保険会社で働くことになった織田裕二さんが演じる主人公がお客様にお茶をいれます。お客様役のジュディ・オングさんが手厳しく、主人公がいれたお茶にダメ出しをします。
私の場合、先輩に言われて書類のコピーをとり、ホッチキスで止めたところ、紙を投げられました。紙を投げた人ではなく、自分のメンターだった先輩に何が悪かったのかと聞いたところ、教えてもらったのは以下のことでした。
- ①右利きの人が多いことを前提にすると、右手はペンを持っているので、紙は左手でめくる。だから、紙の左上でとめておくとめくりやすい
- ②ホッチキスの針を斜めにとめるのは破れにくいから。針を縦にとめると針の下側から破けやすく、横にすると針の右側からやぶける
私のメンターは穏やかで理詰めで考える人だったので、上のようにわかりやすく教えてくれました。もちろん、紙を投げた先輩の態度については、問題外だから忘れるようにとも言われました。
日本企業の新人研修
最初に勤めた企業で、毎日雑用をしながら考えたことがあります。
「どうして日本の企業では、大学を出てもバイトのような雑用をやらせるのか?」
そのことを考える材料になったのが、ホッチキスのとめかたです。
メンターの先輩が教えてくれたことは、「資料を使う人の立場になって考える」ということです。
めくりにくく、紙が破けやすい資料は使い勝手が良くありません。小さな仕事でも、先のことを想像して考える癖をつけろ、という教えです。
お茶くみについても、飲みやすい温度、商談を邪魔しないタイミングなど、考えるポイントがいくつも出てきます。
大きな仕事をするには、そういう初歩を学びなさいというのが日本企業の研修の一部になっていると思います。
丁稚奉公のような研修は必要なのか
社会人一年目の日々から15年くらいが過ぎたある日、小さな驚きを覚える体験をしました。
新しい職場に置かれていた複合機は、ホッチキスでとめる作業までしてくれるという優れものでした。
タッチパネルからホッチキス機能のボタンを押して、機械が紙を吐き出すのを待ちました。すると、ホッチキスは、紙の左上に縦にとめられていました。
ところが、針が斜めではないのです
先輩に渡した書類がオフィスを飛んだ日を思い出しました。あの「基準」は一体なんだったのか。
ちなみに、ネットで検索すると、今の複合機は、縦にも横にも斜めにもとめられるものがあります。2か所とめるという選択肢も備えている機械もありました。あの日から思うと、夢のような世界です。
コピー取りやお茶くみに代表されるような日本の研修について話を戻します。
外国企業や国際的なNGOで働く知り合いたちに聞いた限りでは、日本の「丁稚奉公」的な研修をしている会社や組織はありません。
もちろん、研修はありますが、もっと具体的で振り返りが出来るメニューを取り入れています。最近の日本企業でもそのような研修を取り入れているという例は多いと思います。
ただ、日本社会には、「黙って従え。自分で考えろ」というような丁稚奉公の文化は根強く残っていると私は感じます。
日本式「丁稚奉公」 長所と短所
良い面と言えば、自分で考えるということです。
私の場合は安直に答えをメンターに求めてしまいました。ただ、その後も「なんで書類を投げたのかなぁ」という疑問が出発点となり、日本の企業で働くことについて考えるようになりました。
「守破離」という言葉があります。剣道や茶道の修行段階を説明した言葉です。
最初は、師匠に教えてもらった基本を身に着ける。次に、師匠以外から学んだことを取り入れて発展させる。最後の段階では、独自の新しいものを生み出す、という三つの段階です。
お茶くみやコピー取りを考えると、「守破離」を連想します。
おそらく、日本のビジネスパーソンは、こうしてサービスを向上させてきたのだと思います。モノづくりの強さの一因だと私は考えます。
一方、お茶くみやコピー取りという「研修」から生まれる負の側面です。
前提として言っておきますが、すべての人が同じ道を歩む分けではありませんし、統計や研究をしたわけではないので、違う意見があることも承知の上で書きます。
ホッチキスの例から考えると、日本的研修では、ホッチキス自体が不要だとか、紙の書類はいらないという発想が生まれにくいのではないかと思います。
その一例が印鑑です。新型コロナウイルスの流行まで印鑑文化は日本では変化しませんでした。(大学時代、印鑑の有効性の法的根拠を知りましたが、説得力に欠けるように思ったことを覚えています)
ヨーロッパの知人・友人がいますが、何かをする時に、しつこく理由を聞いてきます。
私も理屈っぽい方ですが、「ただの作業なんだから、早くやればいいのに」と思うことがありました。
単純作業に対して、「なんでこんなことをしなければならないのか」という疑問に一定の答えがないと動き出さない傾向が欧米人にはあるように感じます。
疑問を感じない人には、「ホッチキスをなくして、もっと便利な方法で仕事をしよう」という発想が生まれにくいとも考えられます。
まとめ ―考え方はそれぞれ 押し付けはほどほどに―
日本企業で働きにくいという方。もしかしたら、日本的研修や企業文化があなたに合っていないだけなのかもしれません。
真面目に働くのも大切ですが、自分なりに考えて答えを出せば、他人の言うことは参考程度に受け流して十分だと思います。(もし他人の言う事で9割以上の成功を導き出せるという統計結果があれば従う価値はあるかもしれません)
私が書いた例のように、紙を投げられて怒られた仕事の基準が、時間が立つとあっさりひっくり返されることだってありますから。
逆説的に言えば、私が書いた今回の記事も、あっさりひっくり返るかもしれませんのでご用心を。







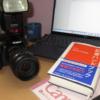
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません