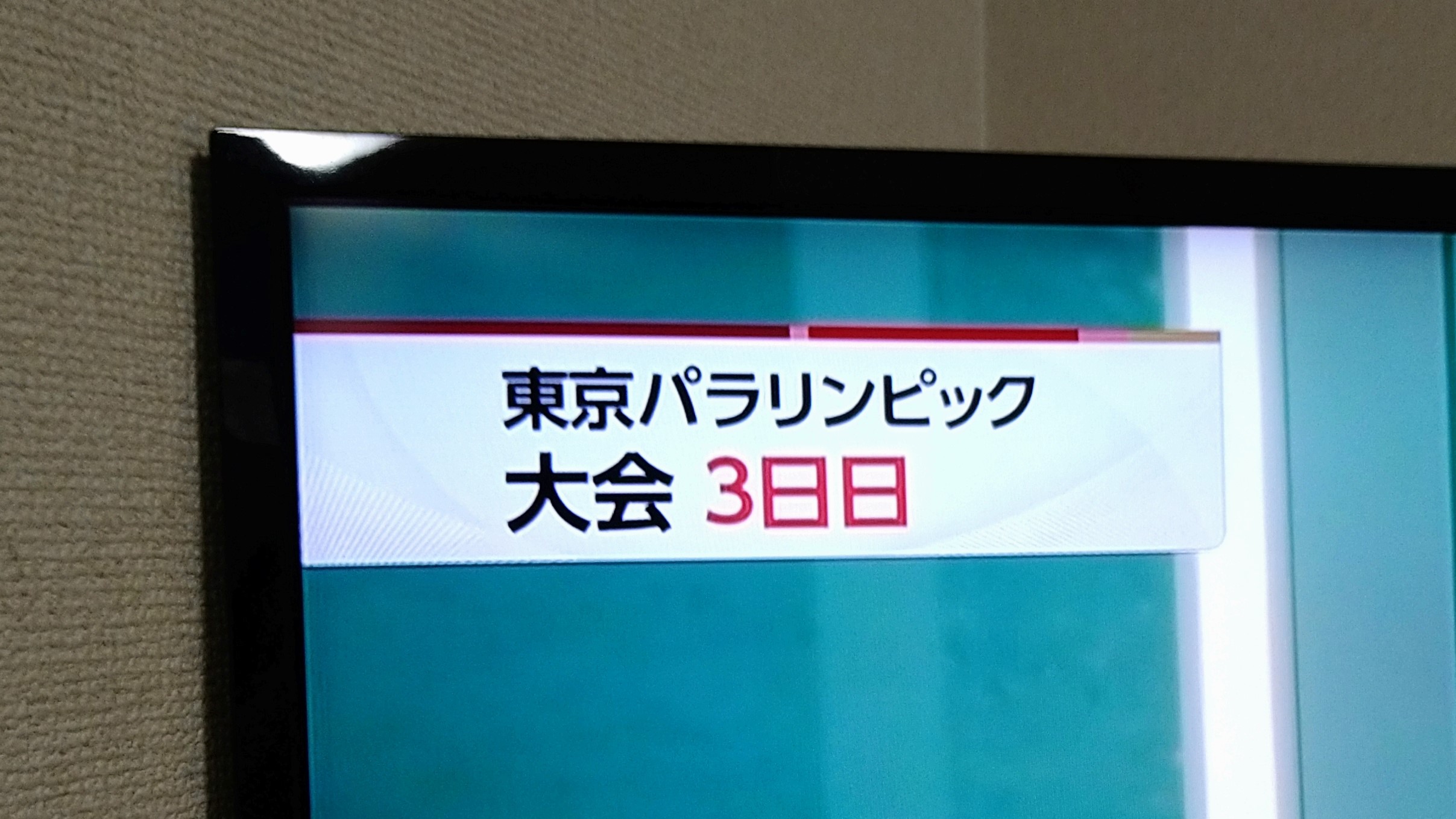
精神論だけでは不十分 誤字脱字をなくす方法3選
ライティングでなくしたい誤字と脱字。今回は、誤字脱字を減らす方法をご紹介します。
こんにちは、社長の藤田です。かつてとある新聞社に勤めていましたが、2021年に退職。現在はフリーランスのライターとして活動しています。
ライティングにおいて、意図的に誤字脱字をしようとしている人はほとんどいないと思います。気をつけて書いているにもかかわらず、どうしても発生してしまう。それが誤字脱字です。
現にこの文章においても、誤字脱字を「誤字達治」と打っていました。この文章を書いたのがちょうどワールドベースボールクラシック(WBC)の開催時期で、侍ジャパンの一員であるラーズ・ヌートバー(日本名・榎田達治)選手について調べたからだと思います。
余談はこれくらいにして、本題に入ります。
序論 ―「精神論」だけでミスは防げない―
ウェブ上には、ライティングのノウハウについてのサイトが無数にあり、「誤字脱字を防ぐには」といった記事も多く見られます。
「たった一言でも誤字脱字があるだけで、ライター自身の信頼はもちろん、その文章を公にしている企業自体の信用が一気に失われます」。このような厳しい論調で、誤字脱字を戒めるサイトもあります。
これらのサイトでは、誤字脱字の撲滅策として、次のような手段が紹介されています。
・間違っている前提でチェックする
・見直しの際に疑って掛かる
・同音異義語に注意する
・少し時間を置いてからチェックする
・集中してチェックする
ここに挙げた手段も、文章の見直しをする上で確かに重要なのですが、ほとんどのライターは当たり前のように心掛けていると思います。それでもミスが減らないから、困っているのです。
精神論だけでは、物事は解決しません。誤字脱字のないライティングで、クライアントや社会の信頼を得るためには、しっかりとした方法を実践することが必要です。
本論 ―誤字脱字を減らす方法3選―
そこで、上記の「心構え」はすでに行っているとの前提で、さらに誤字脱字を減らすためのテクニックを三つ紹介したいと思います。
原稿を印字する
文章のチェックをパソコンの画面で行っている人は、プリンターなどで印字することをお勧めします。こうすれば、格段に誤字脱字を見つけやすくなります。
文章を打ち出せばミスに気付きやすいというのは、長くライターをしている人ならば実感している人も多いと思います。この経験則に対し、学術的にアプローチした研究があります。
メディア研究の第一人者とされるカナダの批評家マーシャル・マクルハーンは、パソコンやテレビの画面から直接目に入る「透過光」と、自然光や照明の光が紙に反射して目に入ってくる「反射光」の性質の違いによって、人間の脳や心理に変化が出るという仮説を述べました。
マクルハーンの説をざっくり説明すると、透過光の場合、脳は入ってきた映像情報をそのまま受け止めるため、細かい部分無視してしまう。そのために間違いを見落としやすい。
一方反射光の場合、脳が「批判モード」に、心理状況は「分析モード」になるため、紙で印刷した文章を読むときは細かい間違いに気付きやすくなる-というのです。
第三者に読んでもらう
小難しい学説は抜きにして、書き手以外の第三者に目を通してもらうというのは、手っ取り早く、かつ効果的な手段です。
書き手がどんなに間違っているという前提でチェックしても、どうしても先入観から間違いを見落としてしまいがちです。
その点第三者なら、先入観がありませんので、細かな間違いにも気付きがちになります。
日本のことわざに「傍目八目」というのがあります。囲碁からきた言葉で、「目」は1個の碁石の意味。対局している当事者よりも、傍らで見ている人のほうがいろいろなことに気づき、八目先まで見通すことができるということを表しています。文章チェックにおいても、まさに同じことが言えます。
新聞の編集では、記者が書いた原稿はデスクと呼ばれる責任者のほか、新聞紙面をレイアウトする整理担当者、できた紙面をさらに確認する校閲担当者など、複数の人のチェックを経て記事になります。書籍の編集においても編集者や校閲者の目を通します。
間違うパターンを自覚する
ある程度の文章を書いて、そして誤字脱字を繰り返しているうちに、ミスのパターンが見えてきます。自分が頻繁に行うミスのパターンを自覚し、重点的に確認することで間違いに気付きやすくなります。
新聞紙面を「新聞誌面」というように変換ミスをよく行う人、「わたshの名前はフワちゃんです」というように母音(この場合は「i」)を打ち損じる人など、いろいろなパターンがあると思います。
私がよく行うミスは、濁点(゛)を付け忘れたり、逆に不必要な濁点を付けたりすること。冒頭に挙げた「脱字」を「達治」としてしまったケースや、ほとんどを「ほどんど」と書いてしまうパターンです。
「ローマ字変換で打っているよね? どうしてこんな間違いをするの?」。記者時代、上司からあきれられたこともありましたが、間違いをする原因は得てして本人でも分からないものなのです。
必要経費と手間を惜しまないこと
私はフリーランスとして自宅で仕事を始めた当初、しばらくはパソコンの画面で原稿をチェックしていました。記者時代はプリントアウトしていたのですが、零細個人事業主としては、プリンターのインク代と用紙代の節約する必要があったためです。
しかし仕事を重ねていくうち、打ち出して確認する方式に戻りました。インクの減りは確かに早くなりましたが、余り気にしていません。ケチることのできない必要経費だと考えています。
また、内容がそれほど専門的でない原稿の場合は、可能な限り妻にチェックしてもらっています。これは効果てきめんで、バシバシ間違いを見つけてくれます。もちろん守秘義務がありますので、全ての原稿というわけにはいきません。
よい成果物をつくるためには、やはり必要経費と手間は惜しんではいけないと思います。
まとめ
今回は、誤字脱字を防ぐ「心構え」として、次の項目を挙げました。
・間違っている前提でチェックする
・見直しの際に疑って掛かる
・同音異義語に注意する
・少し時間を置いてからチェックする
・集中してチェックする
ただ、精神論だけでは不十分。ということで、具体的な方法として、次の三つをあげました。
・原稿を印字する
・第三者に読んでもらう
・間違うパターンを自覚する
誤字脱字をして、得する人は誰もいません。撲滅に向け、努力を重ねていきましょう。






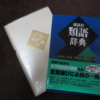
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません