
座談会や対談の取材方法は? ー複数人への同時インタビュー テクニック7選ー
インタビューなどにおいては、取材対象者が必ずしも1人とは限らず、場合によっては1人で大勢の話を同時に聞くということもままあります。
こんにちは、社長の藤田です。2002年から14年間、地方新聞社で記者職に従事。2021年からフリーライターとして活動しています。
複数の人たちへの同時取材は、場が和んでさまざまな意見を聞くことができる反面、話がとりとめのない方向に向かったり、誰が何を話したか分からなくなったりする危険性もはらんでいます。
今回は、通算16年間で数多くの人たちを取材してきた経験を元に、座談会、対談、コメント収集など、複数人を相手に取材する際に注意するべき点を紹介します。
なお、以前仮面ライターさんが「意図せずに複数人に囲まれてしまった際の取材の仕方」を紹介しています。新聞記者など、取材のプロ向きの内容です。こちらもご参照ください。
メリット
まず、複数人の同時インタビューのメリットについて説明します。
・さまざまな意見が聞ける
・場が和んでざっくばらんに話を聞ける
・取材が一度で済む
さまざまな意見が聞ける
「3人寄れば文殊の知恵」という言葉がありますが、何人かが集まって話をすることで、さまざまな切り口の発言や思いもしなかった意見が出て、執筆する記事に深みを持たせることができます。
場がなごみ ざっくばらんな話
一つのテーマの取材で集まる人たちは、サークル仲間、会社の同僚など、顔見知りであることが多いです。場が和むことでざっくばらんに本音を聞き出すことができます。
「取材対象者同士で言い争いをする可能性もあるのでは」という心配もあるかも知れませんが、私が経験した限りは複数人の取材でけんかに発展したことは一度もありません。
取材が一度で終わる
取材する側の効率面での話ですが、一つの場所に集まっていただくことで、一度に取材を済ませることができます。
陥りやすい点
1対1の取材にはない注意点もあります。
・誰が何を話したか整理が必要
・発言内容が重複する
・疲れる
誰が何を話したか整理が必要
複数の人が話しますので、誰が何をしゃべったかを把握していかないと、記事を書く際に困ります。対談や座談会形式の記事はもちろん、第三者表現の原稿でもかぎ括弧でコメントを記す際に発言を取り違えないよう注意が必要です。
発言内容が重複する
「さっきの人と同じです」「あー、言おうと思ったのに先に言われた」
複数人取材の際、対象者からよく聞くフレーズです。発言者のコメントがみんな同じようなものになってしまい、中身のない取材になる危険性があります。
疲れる
複数人を一度に取材するのは、結構体力を消耗します。1回の取材時間が長くなることも多く、終わってからぐったりしてしまうこともしばしばです。
複数人相手の取材 ーテクニック7選ー
複数人を一度に取材する際に心掛けることやテクニックについて、いくつか挙げてみたいと思います。
座席表を書く
まず、話を聞くに当たって、どこに誰が座っているかという座席表を書くようにします。特に座談会などの取材は写真を撮影することがほとんどですので、キャプションを書く際にも役に立ちます。
座席表には、その人の特徴を書くと執筆の際にイメージがわきます。「眼鏡の男性」「茶髪の女性」などという外見でも良いですし、「甲高い声」「関西なまり」といったように声のタイプを書いておけば文字起こしの際に役に立ちます。
ただし、「頭髪の薄い男性」などと書いているのが取材相手に見えてしまうと、気まずくなりますので留意してください。
録音する
取材の際に先方の了解を取って録音することは多いと思いますが、複数人に対する取材では必須です。一度にしゃべられた場合、メモが絶対追いつかなくなります。
発言者の声の特徴をつかんでおけば、テープを後で聞き返して誰の発言かを特定することができます。
たまにですが、声質の似た人が同席する場合があります。その場合は「○○さんはどう思いますか」「次は××さんお願いします」と意図的に固有名詞を声に残すようにすればよいです。
質問事項をいつもより多く用意
取材対象者の発言が重複することを考えて、質問事項はいつもの取材より多く用意したほうがよいでしょう。
発言の重複を恐れない
とはいえ、顔見知りや会社の同僚など、同じような考えを持った人が集まれば、発言が重複することは仕方がありません。
「陥りやすい点」の項目でも触れたように、内容が被ってしまい、取材対象者が発言をためらうシーンがよくあります。そんなとき「内容が被ってもいいですよ。○○さんのお言葉で」などと発言を促すようにしてみるとよいです。切り口の異なる、記事に使える発言が案外出たりするものです。
発言の少ない人から意識的に話を引き出す
みんながみんな、取材に慣れているとは限りません。発言の多い人、少ない人がどうしても出てしまいます。私の妻のように、顔見知りにはいろいろおしゃべりするのに知らない人と話すのは苦手な人も多くいます。
その際は、あえて発言の少ない人に水を向ける必要があります。そうしないと、特定の人だけがしゃべっているような記事ができあがってしまいます。
話を聞く順番をローテーションする
発言の順番を同じにすると、どうしても後から発言する人のコメントが前の人の“後追い”となってしまいがちです。取材対象者から記事に使える発言をまんべんなく引き出すためには、定期的に発言する順番を変えるのが効果的です。
向かって右から発言してもらった後は、左から発言してもらう。場合によっては名前の五十音順など、取材に支障を来さない範囲でランダムにしてみるのも面白いかもしれません。
前日は早く寝る
「陥りやすい点」で挙げたように、複数人から一度に話を聞くのは疲れます。若い頃はそうでもなかったのですが、40歳を過ぎるとさすがに体に応えます。
前日は夜更かしや深酒などはせず、早く寝て十分な休息を取り、体調万全で取材に臨んで下さい。
まとめ
今回は、座談会や対談の取材で使える 複数人への同時インタビューで心掛けること・テクニックを紹介しました。まとめです。
①座席表を書く
②録音する
③質問事項をいつもより多く用意
④発言の重複を恐れない
⑤発言の少ない人から意識的に話を引き出す
⑥話を聞く順番をローテーションする
⑦前日は早く寝る
この方法を実践することで、6人くらいまでは一度に話を聞くことができると思います。7人(説によっては10人)の話を一度に聞いたとされる厩戸王(聖徳太子)までとはいきませんが、あと一息のところまで近づくはずです。
聖徳太子を目指して、頑張りましょう。



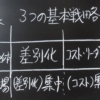




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません