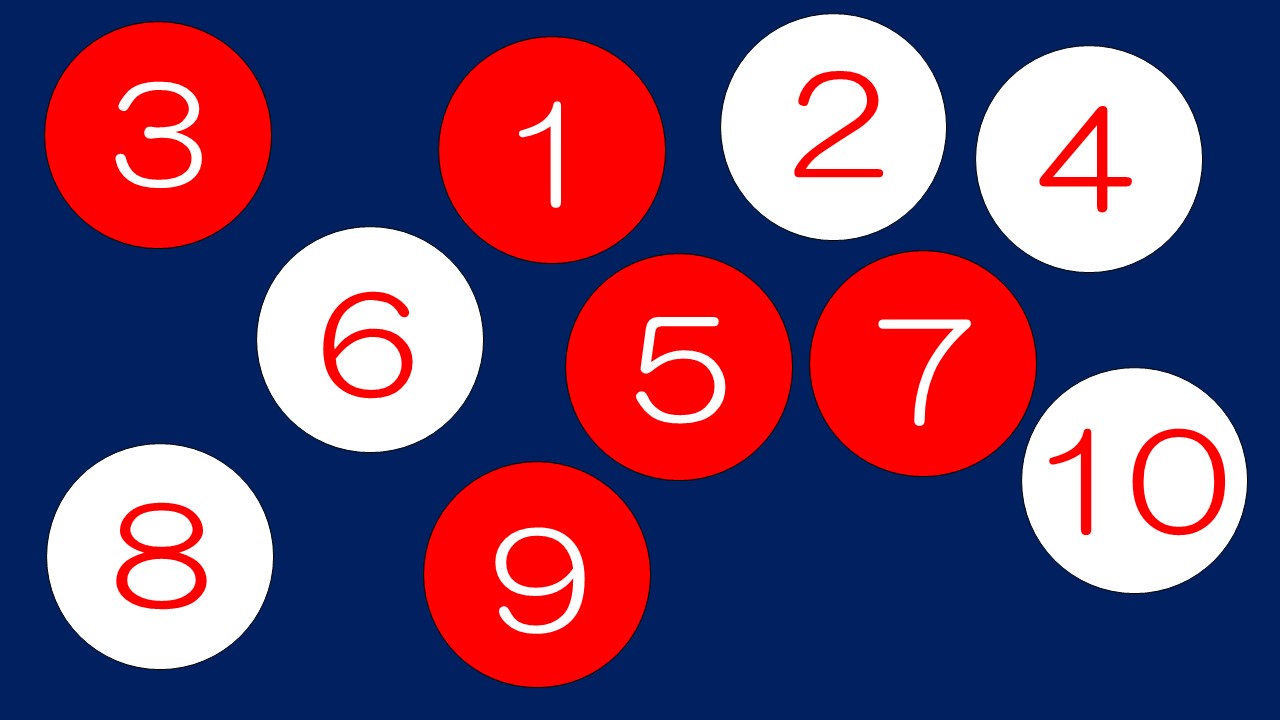
罵倒の嵐 地獄絵図のゲートボール大会
仕事で、私生活で、あるいは趣味で、嫌々ながらやっていることや、惰性で続けていることはありませんか。
こんにちは、社長の藤田です。現在フリーライターをしていますが、かつては地方新聞社で働いていました。
記者時代、とあるゲートボール大会の取材をしたことがありました。近隣市町のチームが集まる程度の小さな大会で、新聞の地方版の隅っこに、短い記事と小さな写真が掲載されるような行事でした。
にもかかわらず、取材から何年も経っている現在も、そのときの殺伐とした雰囲気ははっきりと覚えています。「この人たちは何のためにゲートボールをプレーしているのか?」。そのような疑問が、今も脳裏にこびりついています。
今回は、ゲートボール大会の取材を振り返り、今思うことをつづっていきます。
子どもの頃から身近だったゲートボール
本題に入る前に、ゲートボールのルールと子どもの頃の思い出について簡単に触れたいと思います。
当時、実家の近くに小さな広場があり、近所の高齢者がよくゲートボール楽しんでいました。その中には私のひいおばあさんもいました。子供会と老人クラブの交流行事で、一緒にプレーしたことも覚えています。
ゲートボールは5人対5人の団体戦。スティックで玉を打ち、三つのゲートを順番にくぐらせ、最後にコートの真ん中にあるポールに当てれば上がりです。くぐったゲートの数に応じて点が入り、上がると高得点がもらえます。
また、敵または味方の玉に当たると、スパーク打撃という特殊な打ち方で、敵の玉をコートの外に出して妨害したり、味方の玉を有利な場所に移動させたりすることができます。
小学校のクラブ活動でも、私はゲートボールクラブに所属しました。子どもにとって玉をまっぐに打つのは容易ではありませんでしたが、上がりを目指して次のゲートを目指していきました。
人より先に上がると、他の子どもたちから羨望のまなざしが向けられました。味方をアシストして、チームメイトから「おー、ナイス」「さすが藤ちゃん」などと褒めてもらえ、うれしかったことが今も記憶に残っています。
取材した大会は地獄絵図そのもの
そんな楽しい思い出があるゲートボールですが、取材で見たプレーの光景は、阿修羅に支配された地獄そのものでした。
相手の邪魔をするのがセオリー
まず、上がりを目指しているプレーヤーは一人たりともいません。自チームの点を増やすことは二の次で、試合の最後までコートに残っていかに敵チームを邪魔するかが試合運びのセオリーとなっていました。
隙あらば自分の玉を敵に当て、スパーク打撃で場外に飛ばす。そして敵チームも同じように妨害をする。まさに足の引っ張り合いの泥仕合が繰り広げられていました。
「相手の邪魔をして、自分たちがいい思いをするとんでもねぇゲームだ」。毒舌で知られる希代の落語家・立川談志師匠は、ゲートボールをこのように評したと言います。まさに言い得て妙です。
ただこの後、次のように続けたそうです。
「だから俺に向いている」
リーダーがチームメイトを罵倒し続ける
戦い方以上に、出場チームの雰囲気は最悪でした。
各チーム、リーダー格の選手が1人ないし2人おり、そのほとんどが男性でした。ボールをどこに打つかは、そのリーダーの指示に委ねられており、他のプレーヤーが考えを挟む余地はありませんでした。
そして、狙い通り玉が飛ばないと、リーダーから容赦ない罵声が飛びます。
「どこへ打ってるんだ、下手くそ!」「お前はわしの指示が聞けんのか!」
集中して罵られる選手が各チーム1、2人おり、例外なく気の弱そうな人。終始死んだ目でプレーしていました。中には、リーダーに聞こえないような小声で何か口答えをしているような女性もいましたが、本人に面と向かって反論するような人はいませんでした。
関係者には申し訳ないが事実です
このような文章を書き、ゲートボールを趣味としている方、関係者には不愉快な思いをさせたと思います。他の大会はもっと和気あいあいとしており、チームの雰囲気もよいのかもしれません。
しかし、上記はすべて事実です。私が取材したゲートボールは、私の原風景の中にあるそれとはずいぶんかけ離れたものだったのです。
「なぜ続けているのか」という疑問
「なぜこの人たちはゲートボールを続けているのだろう」
取材をしながら、このような疑問が湧き起こりました。
怒られ続けながら試合をしたところで、楽しいはずもありません。早く辞めればいいのに。それともひょっとして、怖いリーダーに脅されて辞めるに辞められなかったのでしょうか。
リーダーにしても、罵詈雑言を吐きながらプレーするのは楽しくないでしょう。中にはそれをこの上ない楽しみと感じる頭のおかしい人間もいるかもしれませんが…。
「結局のところ、惰性で続けているだけではないだろうか」
取材帰りの車の中で、このように結論づけました。
惰性で続けていること 身近にありませんか?
ただ、このゲートボール大会は決して人ごとではありません。嫌々ながらやっていることや、惰性で続けていることは、私たちの身近にもあるのではないでしょうか。
一例を挙げると…
・上司や取引先からパワハラを受けながら職場を辞めないでいる会社員
・割の合わない案件や赤字の仕事を惰性で受けているフリーランス
・たいしておいしくもないラーメン店に何となく通っている人たち
・家計が見直されることもなく、毎月銀行口座から自動引き落としされる生命保険の保険料
お金を稼ぐ必要があるから、将来につながることだからと割り切るのなら、我慢して続ける価値は大いにあると思います。しかし嫌な思いをしてまで本当に続ける必要があるのか、一度整理してみる必要はありそうです。
怖いリーダーや、死んだ目をした選手にならないために、常に今の自分を見直し続け、「何のために行うのか」を自問自答することが大切なのではないでしょうか。


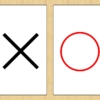





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません