
学歴も会社も頼れない ライターに限界はあるか
みなさん、こんにちは。フリーライターの定年について、弊社の社長が以前、ブログを書きました。私たちの想像を超えて反響があり、掲載後も時々このテーマについて考えています。
今回は、社員である仮面ライターの経験から、このテーマについて書きたいと思います。
最初に結論を言うと、「フリーライターに定年はなし」です。社長と社員で意見が違いますが、自由な社風と捉えていただければ幸いです。
社長執筆のブログ記事とは
まず、弊社の藤田勝久社長が書いた記事をご存知ない方もいらっしゃるので、その記事を紹介いたします。
「フリーランスの定年」という題で、前編と後編に分かれています。
「『フリーライターに定年なし』は幻想」とか、「短かった『我が世の春』」などの見出しで、記事が展開されています。
石原慎太郎氏の小説から考えた
弊社社長のブログ記事の中に、ある高齢女性のエッセーと、故・石原慎太郎氏の小説の話が出てきます。
社長のブログを読んで、「なるほどなぁ」と思ってしまいました。両者とも、力が衰えたのではないかという説です。
私の好きな小説家が書いたエッセーでも、社長が言うような現象を見たことがあります。どこかで書いていたことをまた出してきたので、がっかりしました。また、漫画でも、過去に書いた話をほぼ同じように使った方を知っています。
脱線しますが、故・赤塚不二夫さんは、自身の晩年、自分が生み出したキャラクターを描けないというシーンをテレビで見たことがあります。そのシーンは、YouTubeの動画にもアップされていたことがあります。
※酒が好きな赤塚不二夫さんのことですから、どこからが本当でどこまでがギャグなのかはわかりませんが。
ちょっと立ち止まって考えてみました。故・石原氏や高齢のエッセーストの2氏についてです。2人に対して、周囲の人が意見を言えなくなった、ということは考えられないでしょうか?
もしそうだとしたら、そのような立場になったライターは、自分を厳しく見つめなければいけないのかもしれません。
もちろん、自己制御が出来なかったという点を含めて、社長が言う「限界」というのはあるのかもしれません。
逆に言えば、自分を厳しく律し続けることが出来れば、「限界」はやって来ないのではないでしょうか。「初心を忘れず、奢らない」ことが重要なのだと思います。
私も十分に「おっさん」の部類です。自分が初心を忘れて奢っている人間とわかっていながら、あえて書きます。
図々しい仕事をする「おっさん」「おばさん」は、たくさんいます。そういう人たちは、年功序列の優越的地位を利用して、本来自分がやるべき仕事を他の人に押し付けます。(役職がついている人に顕著です)
もちろん、事前の細かい作業や確認まできちんとやり遂げる、「おっさん」「おばさん」はいらっしゃいます。
体力の衰えなどによって、図々しい仕事をする、または、筆力が落ちたと言われる仕事をする人はいると思います。ただ、これは、ある程度、仕事への向き合い方で補えるのではないでしょうか。
江川卓のホップから考える「限界」
読売ジャイアンツの元エースで江川卓さんが投げるボールは、ホップしていたという伝説が残っています。
実際にはホップしていないという趣旨のことを、江川さんご自身がYouTubeなどで発言されています。(※YouTube「江川卓のたかされ」【ストレート論】江川卓のストレートの投げ方・握り方大公開!良い直球を投げたいなら絶対に〇〇を練習しろ!)
江川さんの投げる球は、沈みが他の投手の球よりも少ない上に、インハイにコントロールよく投げ込まれるので、ホップしているように錯覚した、という解説をよく耳にします。
前章で書いた「仕事への向き合い方で補える」という方法は、江川さんの「ホップ理論」から考えました。
人間が持っている、体力、気力、知力は、加齢と共に落ちていくのだろうと思います。ただ、他の人よりも「落下」が緩やかであれば、上がっているようにさえ見えるかもしれません。
未完成の人間の優越的ポジション
私自身のことで言うと、藤田社長が言っているような、取材上の体力や能力は、私にはそもそもなかったような気がします。
取材音源を聴き直すことはしょっちゅうでした。もちろん、自分が興味を持って取材してきたことや、事前調べがしっかりできているの話は、取材が終わった時点で書き始められました。でも、つまらないと思っている話で、デスクに言われたから取材に出かけた時は、からっきしダメでした。
筆力については、私の書いたブログを読んでいただければわかるように、はっきりいって大した力はありません。
そんな私でも原稿の書き方がわかってきた時期がありました。それは、「整理部」という取材をしない内勤職場への人事異動を言い渡される直前のことでした。
その頃していたことは、意外に簡単なことです。時間の限り何度も推敲し、納得するまでおかしな部分を書き直す。場合によっては追加取材をする。それだけのことでした。そうすると、デスクが注文してくることはなくなりました。
その後、久しぶりにライターに復帰すると、そういう「謙虚な」仕事をしていない日が度々ありました。そして、ピークが来る前に戦力外となりました。
筆力低下を防ぐには
記者をクビになった私ですが、その後はブログや小説を書いています。
そうした日々の中で気がついたことがあります。
体力は気力を補い、気力は知力を補う
「体力」「気力」「知力」の順番は、入れ替えても成り立つと思います。
「かく企画」のブログのカテゴリー一覧に「仕事」があります。その中に「自己管理」という分類を設けています。その中で、ロック・ミュージシャンの自己節制について考察した回があります。
私の経験では、週に数回の運動、朝の散歩、飲酒コントロールをするようになってから、それほど体力の低下はないように感じています。
もちろん、20代、30代の頃より、関節が傷んだり、病気がちではあります。ただ、出来る範囲で続けていると体力は維持できています。
そして、体力につられて、気力というか精神力も維持出来ています。精神力には、新しいことをやってみるという気持ちや継続力も含まれています。
記憶力は落ちないのか? そして知力は?
別の回で紹介したYouTuberで精神科医の樺沢紫苑さんが、ご自身のYouTubeで次のようなデータを紹介しています。
―20%の高齢者が大学生と同じ記憶力を持っていたー
―60歳以上の高齢者の中で、大学生よりも記憶力が高い人が数パーセントいたー
YouTubeで「樺沢紫苑」「加齢」などで検索すると、老化をテーマにした回で樺沢さんが話をされています。
記憶力は落ちると決めてかからず、インプット、アウトプット、フィードバックを繰り返すように私は心がけています。記憶力が悪かった私ですが、2022年には、暗記ものの資格試験に合格(※その体験は別の回で紹介しています)しました。
記憶力に支えられているかわかりませんが、知力については、ほとんど衰えを感じていません。もしくは、20代、30代より良くなっているように思います。
それは、もしかしたら私が小説を書いているからかもしれません。ただ、小説を書かない人でも、知力がアップしているという方はいるのではないでしょうか?
理論や理屈を考える面白さは、年齢を重ねてからより深く味わえるのかもしれません。
私の場合は、読書や「かく企画」の仕事によって、知力が鍛えられていると思います。社長と仕事について議論します。仮説を立てて、事を進めて、その結果を振り返る。書籍は読んで終われリではなく、「かく企画」の会議で内容について話しています。
まとめ ―フリーライターの定年とはー
話を最初に戻します。
フリーライターの定年は自分で決めるものだと思います。20代、30代と同じようには書けなくなる。でも、加齢と共に若い時になかったものが自分に身についていく可能性はあります。
それはプロ野球の投手と似ているのかもしれません。「体力」が落ちてきたら、配球の組み合わせやタイミングの取り方で相手を封じ込める。でも、そのような投球は若い時には出来なかったことです。
プロ野球の選手は、球団から不要と言われたらユニフォームを脱ぐ。それでも諦められなければ、トライアウトを受けたり、独立リーグに行ったりする。
仕事がなくなった時、自分がユニフォームを脱ぐことを決めたら、ライターの定年なのではないでしょうか。

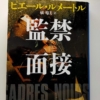



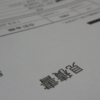

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません