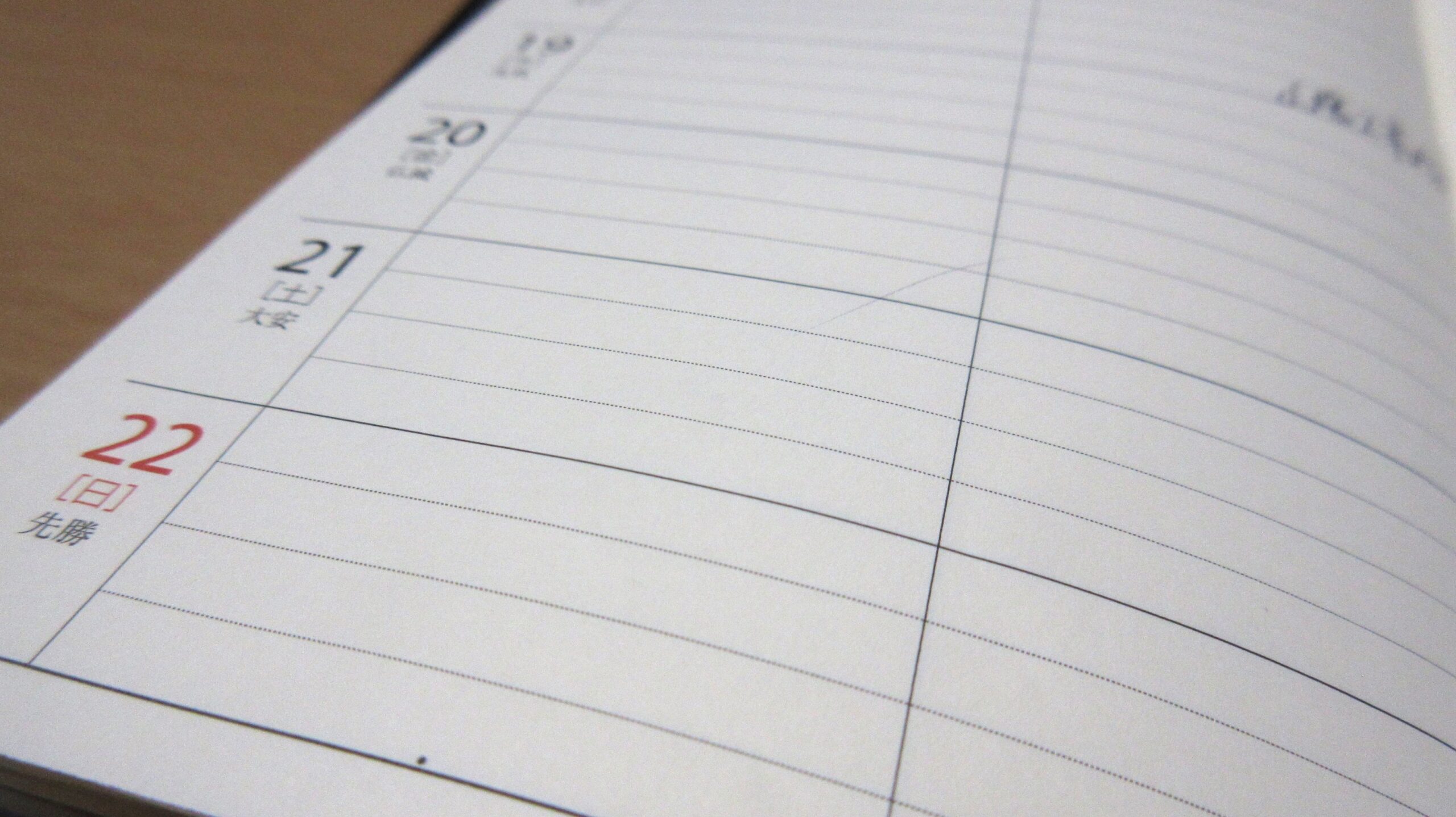
予定づくりのプロ 実行は大の苦手
「かく企画」社員の仮面ライターです。独立や副業、スキルアップのために私たちがやっていることを紹介していますが、今回は計画づくりについて考えたみたいと思います。
私は予定を立てるのが趣味のようなものです。
始まりは小学4年生の夏休みだったと思います。だらだらと過ごさないように一日の計画を立てるように言われました。コンパスで円を描いて24時間を円周上に書きました。6時半起床、集合住宅の廊下を掃除し、ラジオ体操。朝食後は勉強を1時間……。
結局、朝起きられなくて、ラジオ体操開始のぎりぎりの時間に集合場所に行く始末。母にしかれらていました。
中高生になると、定期試験の前に計画を立て、ほぼ毎日立て直していました。計画を立て安心する。この計画通りできれば大丈夫だとわかっているのに、すぐに眠くなってしまうのび太くんのような人間でした。
計画を立てなかったころ
仕事を始めると、月間の予定を立てることはしなくなりました。特に、入社一年目は先輩から指示された仕事を忘れないように手帳にメモをするだけでした。転職をして記者になっても同じようなものでした。もしくは、まったく計画を立てなくなりました。理由は計画を決めても無駄だからです。事件や事故が起これば、すぐに出かけなければいけない生活でした。
一応、月初めに宿直勤務と休みの日が書かれたシフト表が配られます。でも、宿直以外、そのシフトが実行されることはほぼありませんでした。
事件や事故が発生した緊急時に休みが飛ぶのは前提でした。実際は、緊急ではない取材でも当然のように出かけなければいけませんでした。だから、計画を立てるという発想がありませんでした。
一流のプロになりたくて
計画を再び作るようになったのがいつかははっきりしませんが、新聞の編集作業をする内勤になったころかもしれません。この職場では、シフトは守られていました。未明まで働く朝刊担当と、朝5、6時から起きて出勤する夕刊担当がありました。
このころ、商社マンなどをされてきた三輪裕範さんが書かれた「四〇歳からの勉強法」(ちくま新書)を読みました。私が刺激されたのは、多摩大学長を務めれた中谷巌さんが言われたことを引用した部分でした。
―― 一流のプロになるためには1万時間を投資しろ ――
大学でも大学院でも中途半端にしか学んでいませんでした。当時は30代半ば。今からでもなんとかしたいと思いました。
次に、どうやって勉強をする時間を作り出すかということが書かれていました。毎朝1時間と、土日の2日に最低3時間を確保すると、年間550時間になり、祝日も勉強すると年間で600時間を作り出せるというのです。
計算してみると、もし年間600時間、一つのことだけを勉強したとして、16年以上かかるのです。そこで予定を立てることにしました。
私が勉強しようと決めたのは、大学と大学院で学んだ分野と語学。もう一つ、小説を書くということも目標でした。私は欲張りで一つのことに絞りきれませんでした。このころからこの1年前まで、私は年中行事のように同じことばかりしていました。
年末か年始に、手帳の最初のページに今年の目標を書くのです。また、エクセルのシートで20年先までの目標を書いたり、そのために身につけるべきことをまとめたりしました。
実際に実行されるのは、エクセル表の一番左に書いてある自分の年齢だけです。年は取るけど、ほぼ何も実行されることはありませんでした。
今でも目標が書かれた手帳が残っています。そして、ほぼ毎年更新したエクセル表も残っています。
どうして目標が達成できないのか?
計画を見直しているにも関わらず、私は同じところをぐるぐる回っていました。
一つは自分が作った目標が高かったということがあります。もちろん、高い目標を達成するならば、強い意志を持つことで遂げられるかもしれません。ただ、私には毎日の生活の中で楽しいことを犠牲にしてやり遂げる強さはありませんでした。
その後も、元外務省職員の佐藤優さんが著した「読書の技法」という本などを読み、ちょくちょくインスパイアされることがありました。そういう時は2ヶ月くらい机に向かうのですが、目標のペースには程遠く、年間目標はほぼすべての項目で未達成でした。
不規則な記者生活だったからというのは、出来なかった理由の大きな理由にはなりません。一番の理由は、目標が達成できない理由や原因を考えなかったからです。もちろん、意思が弱いということも理由です。でも、それ以外のことについて考えを巡らせなかったからこそ、10年くらいたいした成果を積み上げられなかったのだとやっと気が付きました。
次回は目標が達成できるようになってきたこの1年について書きたいと思います。





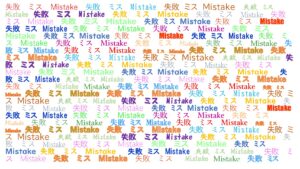
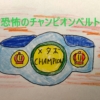
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません