
新聞記者は物知りか
みなさん、こんにちは。元新聞記者で「かく企画」社員の仮面ライターです。突然ですが、新聞記者は物知りだと思いますか?
記者時代、記者の自分は物知りだと思われているように感じたことがよくありました。今回は、新聞記者の「物知り度合い」について考えてみたいと思います。
呆れられた経験 知ったかぶりの怖さ
約20年前の話です。取材で、「ADHD」という言葉を知らずに、取材した人から呆れられたことがありました。
2023年4月時点の「NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター」のホームページによると、ADHDとは以下のように説明されています。
注意欠如・多動症(ADHD)とは、発達水準からみて不相応に注意を持続させることが困難であったり、順序立てて行動することが苦手であったり、落ち着きがない、待てない、行動の抑制が困難であるなどといった特徴が持続的に認められ、そのために日常生活に困難が起こっている状態です。12歳以前からこれらの行動特徴があり、学校、家庭、職場などの複数の場面で困難がみられる場合に診断されます。
NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター ホームページより
それは、ADHDの方を支援している団体メンバーへの取材でした。
「そんなことも知らないんですか? 記者として不勉強ではないですか?」と指摘されました。
おっしゃる通りで、そもそも、ADHDという言葉が取材で出てくる可能性は高いのに、下調べをしないまま、電話取材で話を聞いたことが良くありませんでした。
このような調べ不足は問題外として、記者だった時に、「知っていて当然でしょ」という感じで、自分が知らない言葉や話を耳にすることがありました。
例えを挙げたらきりがありません。新聞で報じられていない、数十年前の町役場での不祥事。太平洋戦争中に中国であった蜂起。新しい経済用語。IT関連の話。
取材で聞きたいこととは関係がないことを取材対象者が話し出すことはよくあります。正直、話を流してしまうこともありました。
ただ、知ったかぶりをして話を進めてしまうと、後で必要だと思ったと時に、聞き直しにくくなった経験が少なからずあります。そこが注意したいところです。
取材前に出来る限りのことを調べておくのは当然です。特に、今はインターネットで簡単に情報を手にすることが出来ます。正確に記事を書くためには、然るべき人や組織に話を聞く必要がありますが、事前準備ではネットによる下調べでも良いと私は思います。
まったく知らない分野の取材 頭を下げて聞き続けた他社の記者
2箇所目の赴任先でのことです。詳細は思い出せないのですが印象的な取材があります。
その取材は、事前準備をする時間がなく、各社の記者が現場に押しかけました。ある新聞社の記者は、該当地域を担当する記者が不在のため、いきなり取材に放り込まれました。
そもそも取材の前提条件からわかりません。その記者は、「すみません」と言い続けながら、前提条件から聞き出し、事の中心まで取材し尽くして去っていきました。
私は横にいながら、その人の質問とその答えをメモし続けました。
記者をしていると、時々そういう状況に置かれます。特に、社会部の記者は、政治部、経済部、スポーツ部、文化部などの専門分野の部が手を付けない話題を取材する機会があります。しかも、その取材は突然に命じられることが少なくありませんでした。
専門記者が一緒にいる時、そもそもの事柄について質問するのは、結構勇気が必要です。自分だけが知らないがために、集団取材の流れを止めてしまうからです。
私は、「すみません」と言い続けながらしっかり取材をした、他社の記者をすばらしいと思いました。それからは、どんなに恥ずかしくても、他社の記者が嫌な顔をしていても、取材対象者に「そんなことを知らないの?」というような圧力をかけられても、知らないことはその場で聞くように心がけました。
もちろん、時には取材が一通り終わってから、不明点を聴き直すこともありました。ただ、前提条件がよくわからないままでは、取材になりません。
突然設定された記者会見などで、前提条件の説明がなければ聞いて当然です。意外なことに、隣りにいる他社の記者もわかっていないということもありました。
話は脱線しますが、弊社「かく企画」の藤田社長は、豆知識を豊富に持っています。社長は1970年代生まれですが、戦後間もなくの生まれかと思うような古い話までよく知っています。
長年の付き合いをしている私からすると、(決してけなしているわけではないのですが)「無駄な知識の総合商社」状態です。「よくもまぁ、こんな話を知っているなぁ」と、感心するやら呆れるやら。でも、新聞記者として損はなかったと思います。
1日1時間の読書
私が新人記者だった頃、先輩記者に「どんなに疲れていても夜に1時間は本を読め」と言われました。その先輩は、普段は下品な冗談ばかり言っていましたが、後輩にパワハラなどをせず(※当時の新聞社では珍しい人でした)、面倒見が良い人でした。
ありがたい助言をもらったのに、当時の私は仕事後に酒を飲んでばかりいました。時々、読書はしましたが、毎日1時間というのは、相当な覚悟がなければ出来ません。
取材先の人たちと「情報交換」を兼ねて夜に飲酒をしていた日々。「酒を飲んでも飲まれるな」の精神で、家に帰ったら30分でも読書をするべきだったのではと今は思います。
そんな私が「物知り」になった時期がありました。その詳細は、このブログの「新聞記者はこうやって新聞を読む ー後編ー」で紹介しています。
当時は、新聞のすべてのページを毎日読んでいました。自分から進んで読んだのではなく、そうしないと、職場でダースベーダーに殺られてしまうからです。
新聞を精読していた頃は、書店に並んでいる、政治、経済、社会問題の話は大概理解できました。現在はその余韻で、当時ほどではないですが、一般的な話を吸収するのに苦労はそれほど感じません。
本題の答えです。
これまで同業他社の記者たちと話をする機会が多くありました。一般的に、新聞記者は物知りが多いとは思います。それは、少なくとも新聞は読んでいるからだと思います。
新聞精読の効果を紹介しましたが、様々分野を網羅しているはずの新聞にも弱点があると思っています。それは、科学の分野です。
「中学生でもわかるように」という前提で多くの新聞社は記事を掲載しています。それが原因なのか、科学の説明を簡単に、しかも限られた行数で書こうとするので、わかりにくいと私は感じます。
想定している読者の科学知識と、取材した内容とのギャップを埋めるのは、なかなか難しいのかもしれません。ただ、現在はインターネット版もありますので、行数に縛られないわかりやすい記事を目にすることも増えてきました。
まとめ ―新聞記者は物知りを目指すべきー
いつものように、脱線しながら話を続けてきました。話を戻し、まとめたいと思います。
インターネットで、様々なことを短時間に調べられる世の中になりました。取材前に事前調べでインターネット検索を使うことは、今回のブログ記事でも勧めています。
しかし、調べてわかるということと、理解して知っていることには、大きな差があります。記者をクビになった身からすると、新聞記者時代には物知りを目指すべきだったと思います。
日々、想定外の分野の顧客を相手に営業活動をしている方も、幅広い知識があって損はないと思います。そのためには、毎日1時間を新書か新聞を読むために使うと良いと思います。
意識していないと物知りにはなれませんし、地道なことも必要です。私も、少しずつでも読書を続けたいと、思いを新たにしました。





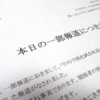


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません